三和油脂株式会社 代表取締役社長 山口與左衛門

米の消費量が減少している現代において、「お米の力=米ぬか」を原料に、こめ油、米糠加工食品の開発、販売に取り組む企業が山形県天童市にある。三和油脂株式会社、同社はこめ油の製造、提供、開発を手掛けている会社だ。今回は、同社の代表取締役社長、山口氏にお話を伺った。これまでこめ油の品質、認知度の向上に尽力してきた。90年代、油の値段が水よりも安くなった時期がある。その時、このままではいけないと感じた山口社長は全国のこめ油メーカーを東京に集め、こめ油の品質向上に向けて旗を振った。その取り組みがあったからこそ新しい技術を確立することができ、今の同社の高い品質を保っている技術力の基盤をつくってきたのだ。同社は創業してから72年間、挑戦を続けており、その立役者は山口社長である。そんな山口社長に同社の強みや今後挑戦したいこと、展望について詳しく伺った。
伝統の継承と、未来への挑戦を可能にする革新企業の本質
"関わる人に情熱を" 地元・社員に愛される企業
三和油脂の社風は同社の名前の由来を体現したようなものであると語る山口社長。3つの和(お客様、地域、従業員)を大事にするという想いが込められ、つけられた三和油脂。実際、こめ油を製造している大手の食品メーカーだけでなく、産学官連携での開発を通して、関わる色々な業界と関係を構築しているのだ。また、地元天童市の中でのこめ油メーカーであり、地元で同社の名前は広く浸透している。地元の方にこめ油を使っていただき、健康づくりを応援していきたいと願っております。そのようなお客様、地元を大事にしている企業だからこそ、従業員にも愛される企業に成長したのだ。山口社長は「従業員のために経営者がいる。従業員が幸せになれるように頑張る必要がある」と話す。日々、誰よりも従業員のことを考え、従業員のために改革を続けている山口社長だからこそ出てきた言葉である。また、「周りの人を考える」という社風は深く同社の中に根付いており、72年という長い歴史を築き上げることができたのであろう。
売らなくても売れるこめ油。高い品質の裏側は
こめ油の高い品質とそれをつくりあげた技術力が同社の強みである。こめ油は他の油とは違い貴重な成分が入っている特殊な油だ。認知症の予防に使われるオリザノールや、若返りの成分であるビタミンEの50倍の抗酸化力があるトコトリエノールなど数多くの貴重な成分が入っているこめ油。その品質の高さから数々のテレビやメディアでも注目されている。また、ただのこめ油ではここまで注目されない。三和油脂のこめ油だからこそ注目されるのである。そのわけは、お客様の要望、世間のニーズに素早く対応することができる同社の高い技術力あるためだ。「こめ油の良さがどんどん広まっている」と語る山口社長。同社はPRをしてほしいとお願いしたことは今までなく、それでも、度々こめ油がメディアで注目され、問い合わせの数も年々増加している。72年間積み上げてきたこめ油の品質に対する熱い情熱やこだわりがあるからこそ、売らなくても売れるという同社の品質の高さを証明するような、通常では考えられない現象が発生している。東北・北海道のNo.1こめ油メーカー
三和油脂が目指すのは、東北・北海道でNo.1のこめ油メーカー。これからさらに東北地方での米づくりが活発になっていくため、米所である東北でこめ油つくりに力を注いでいく方針だ。そのために必要となってくるのが新たな事業の創出である。
山口社長はこめ油をつくる中で発生する副産物を活用できないかと考えている。
現在、同社は研究開発に力を注いでおり、すでに自社にR&Dセンターという研究所を有している。ここで米ぬかを使用したサプリメントの開発やこめ油の成分を美容系の製品に活用するなど試行錯誤を繰り返しているのだ。山形県でこめ油のリーディングカンパニーとして確立されている同社。これからは今まで以上に事業の発展、新規事業の創出を行い、東北・北海道でNO1のこめ油メーカーを目指し挑戦を続ける。いずれ同社の名は全国に広がり、さらには世界に向けてこめ油の良さを発信していくだろう。



挑戦したことと、これから挑戦すること
一番大変だった時期を教えてください
油の価格が水より安くなった時期は大変でしたね。当時、日本がアメリカから大豆や菜種を安く輸入していた時期がありました。その時は、油の値段が1.8Lで特売目玉価格198円で売られていたので、それに連動してこめ油の価格も下がっていましたね。他にも、オリーブオイルのブームが来て、このままではいけないという気持ちがありましたので、こめ油も東洋のオリーブ油にできないか、全国のこめ油メーカーの若手経営者を集めて、新しい技術の創造に挑戦しました。そこから、こめ油の圧搾製法などを開発し、より良質なこめ油づくりに取り組んできました。大変な時期があったからこそ、質の高いこめ油をつくることができたと思っております。これからどんな困難が待ち受けていると思いますか?
現在、原料となる米ぬかの仕入れ量が減っていて、それはこれからも続くと思っています。少子高齢化の影響で米の生産量が年々減ってきているのが原因ですね。実際、30年前の生産量は1000万tあったのですが、現在は700万tと3割もの生産量が減っています。この課題を解決するためにこめ油用の稲作(油糧米)を行っていきたいですね。ただ、国の規定があるので今はできないのですが、米をつくる農地は日本全国で余っているような状況なので、その土地をうまく活用し「水田を油田」にしていきたいと思います。こめ油をつくるという観点だけでなく、日本の食糧自給率を向上させるというところも考えて、前向きな気持ちで新たな取り組みをして参ります。
社員にとっての理想会社とは?
従業員がやめないような、社員が安心して働ける会社にしていきたいと思います。現在、やめる人はほとんどいない状況にありますので、従業員の方々が健康的に災害や病気がないだけで私は満足しております。ただ、従業員の幸せのためにも会社の利益を増やすことは必須だと思っておりますし、利益を増やすことに向けて現場の方たちも一緒にアイデアを出してくれれば嬉しいと思います。こめ油を用いた新しいレシピの考案やこめ油を用いた新しい取り組みなど色々な意見・提案が現場の方たちから上がってくるような状況になれば、今まで以上のスピードでこの会社は進化を遂げていくことができると思ております。

成長を続ける企業の最前線を走る
三和油脂株式会社 総務部次長 門脇英樹
今回お話を伺ったのは、自身の地元である山形県天童市でこめ油の製造を行っている三和油脂株式会社に入社を決めた門脇次長だ。約6年前、中小企業の経営を支えたいという想いを抱いて、中途で入社した。そこから様々な方たちと関わる機会が増え、自分の知らなかった知識や経験を聞くことが自身の成長に繋がっていると感じている。「三和油脂を世界に発信できる企業にする」という夢のために、自身の成長のみならず、同社の成長のためにも挑戦を続けている。その姿はまさに同社の挑戦を続けるという考え方を最前線で体現していると言っても過言ではない。そんな門脇次長に入社理由や現在のやりがい、こめ油の魅力について詳しく伺った。伝統の継承と挑戦の未来を担う社員の思い
自身の夢×会社の未来
自分の思い描いていたビジョンと会社のビジョンが一致していた。門脇課長が6年前に中途入社するときに感じていたことである。前職では金融関係の仕事についており、その業務の中で中小企業と関わる機会が多かった。様々な中小企業と関わることで中小企業への興味がわき、経営を支えていきたいと考えるようになり、新たな業界で自分を成長させるという気持ちが強くなっていった。その中で、地元天童市であらゆることに挑戦している同社に惹かれ中途入社を決断した。地元の企業ということもあり最初から名前は知っていたが、同社のことを知れば知るほど入社意欲は高まった。入社してから自身が思い描いていた以上のスピードで会社の進化を実感している門脇次長。その背景には、挑戦し続けている企業に挑戦したい人が入ったことによる相乗効果があるのだろう。これからも進化を続ける三和油脂。その進化の最前線で門脇次長は挑戦を続けていく。知らないことは成長の源泉
「色々な人と関わることで新たな学びを得る機会が多いです」と語る門脇次長。大学の教授や食品メーカーの方など様々な出会いを自身の成長に繋げているのだ。現在、同社は大学とこめ油の共同研究を行っている。その活動の中で様々な大学の教授と話す機会があり、自分が経験してこなかったことや今まで聞いたことのなかった知識など新たな気付きを学びへ変換しているのだ。また、食品メーカーの方たちと関わることで、新たな人との繋がりができたり、様々な業界のことを知ったりするきっかけとなっている。これからのことについて門脇次長は「今まで通りの仕事をしていれば良いわけではない、今後もカテゴリーを超えた挑戦を行っていく」と話す。その言葉の裏には、入社してから数々の挑戦を続けてきた門脇次長の強い想いを感じた。分からないことであっても学び続け、今後も新たな分野、業界にも参入するだろう。門脇次長の成長は止まることを知らない。天童から世界へ、世界に名が響くこめ油に
門脇次長は自身の夢について「三和油脂を世界に発信できる企業にする」と話す。門脇次長は、この夢を叶えるために社長の掲げている想いを社員全員に浸透させていくのが自分の役目だと考えている。今まで社長の考えを一番体現してきた門脇次長だからこそできることである。世間ではこの夢を後押しするかの如く、こめ油の認知度が上がっている。実際、山形県内のスーパーに陳列されるようになってきているなど地元での認知度は年々上昇。これから大事になってくるのは、いかに全国に向けて同社のこめ油を広めていくかだ。そのために、門脇次長は「こめ油を効果的にPRするために何をすべきなのか、世界的に発信するための仕組み作りを行っていきたい」と話してくれた。同社のこめ油の魅力を誰よりも感じている門脇次長だからこそ、こめ油の良さを広めていきたいと考えているのだ。これからは地域の枠にとらわれることなく、世界規模でこめ油の魅力を広めていくことが門脇次長の思い描いている未来である。


こめ油の認知度を広めるために必要なこと
こめ油の魅力を教えてください
あらゆるものに使える万能な油ですね。体にも良くて、どんな食材にも合うような油です。揚げ物をつくる時もこめ油で揚げると胃もたれしないですね。また、サラダにかけたり、みそ汁に入れたり用途は多岐にわたります。直接飲む人もいるぐらいです(笑)。現在、年々健康志向が高まっているので、こめ油の需要もどんどん上がっています。これからは、お客様のあらゆるニーズに対応できるようなこめ油をつくっていく必要があると思います。こめ油が秘めている可能性はまだまだあると思うので、よりお客様に求められるこめ油、必要とされるこめ油をつくっていくことが大切だと感じております。
こめ油の魅力を広める中で変わってきたことはありますか?
一般消費者に向けた製品の売上が上がりましたね。入社当時は全体の3~5%しかなかったのですが、今では20%ぐらいになっています。入社してから次第にこめ油の良さが世間に認知され始めたと感じております。実際、私が入社した秋にテレビでこめ油が良いという報道がされて、そこから半年間は問い合わせが止まらなかったですね。そこから山口社長の考えをもとに新しく工場を立てて、ホームページをリニューアルさせて、購入サイトも新しくつくりました。今まで以上にこめ油を供給できるようなシステムの構築に取り組みました。そのようなこめ油を広めるための盤石な土台や仕組みづくりをしてきたからこそ、一般消費者に向けた製品の売上を4倍となる20%に増やせたのかなと思います。会社として今後挑戦していきたいことを教えてください
事業の2本目の柱として家庭用のシェアをあげることなど、会社の発展に関与する仕事を行っていきたいですね。より安定した経営をするために必要不可欠な要素だと思っております。現在、考えている案としては、こめ油をつくる中で発生する副産物の活用です。その副産物を再活用するのか、新たな製品として売るのか、今後より詳しい計画を考えていく予定です。企業を存続させるためには、新たな事業の柱をつくる必要があると思います。現在、社長が中心に考えてくれているのですが、経営をサポートしていく意味も込めて、何か自分にできることはないのかと自問自答をし、企業の成長に力を注いでいきたいですね。そして、総務部の次長として会社を支え、従業員が働きやすい環境づくりを行うことで会社の発展に貢献していきたいです。
三和油脂株式会社
1949年10月 三和油脂株式会社を設立
1963年9月 資本金2,500万円に増資
1964年10月 仙台工場の建築及び操業開始
1967年8月 資本金5,000万円に増資
1968年7月 郡山工場の建築及び操業開始
1974年8月 資本金1億円に増資
1997年4月 東根事務所建築及び操業開始
2007年5月 仙台工場の建築及び操業開始
2007年11月 東京営業所開設
2017年6月 まいにちのこめ油充填工場稼働開始
1963年9月 資本金2,500万円に増資
1964年10月 仙台工場の建築及び操業開始
1967年8月 資本金5,000万円に増資
1968年7月 郡山工場の建築及び操業開始
1974年8月 資本金1億円に増資
1997年4月 東根事務所建築及び操業開始
2007年5月 仙台工場の建築及び操業開始
2007年11月 東京営業所開設
2017年6月 まいにちのこめ油充填工場稼働開始
| 創業年(設立年) | 1949年 |
|---|---|
| 事業内容 | 動植物油脂製造業 食用油脂加工業 |
| 所在地 | 仙台工場:宮城県黒川郡大衡村松の平三丁目1-6 郡山工場:福島県郡山市富久山町久保田字下河原101 |
| 資本金 | 1億円 |
| 従業員数 | 100名 |
| 会社URL |
_トプ画.png)

_トプ画.png)


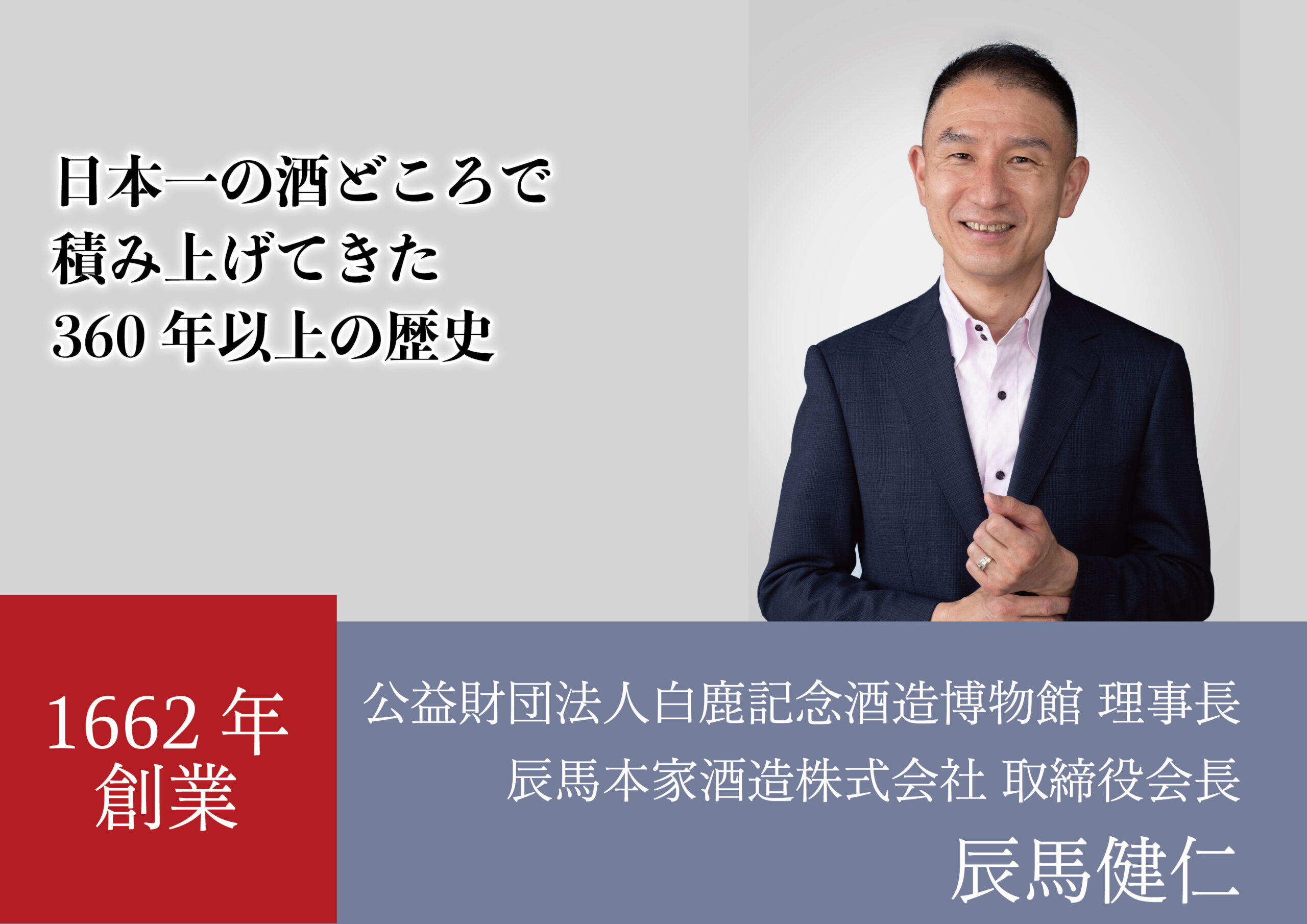
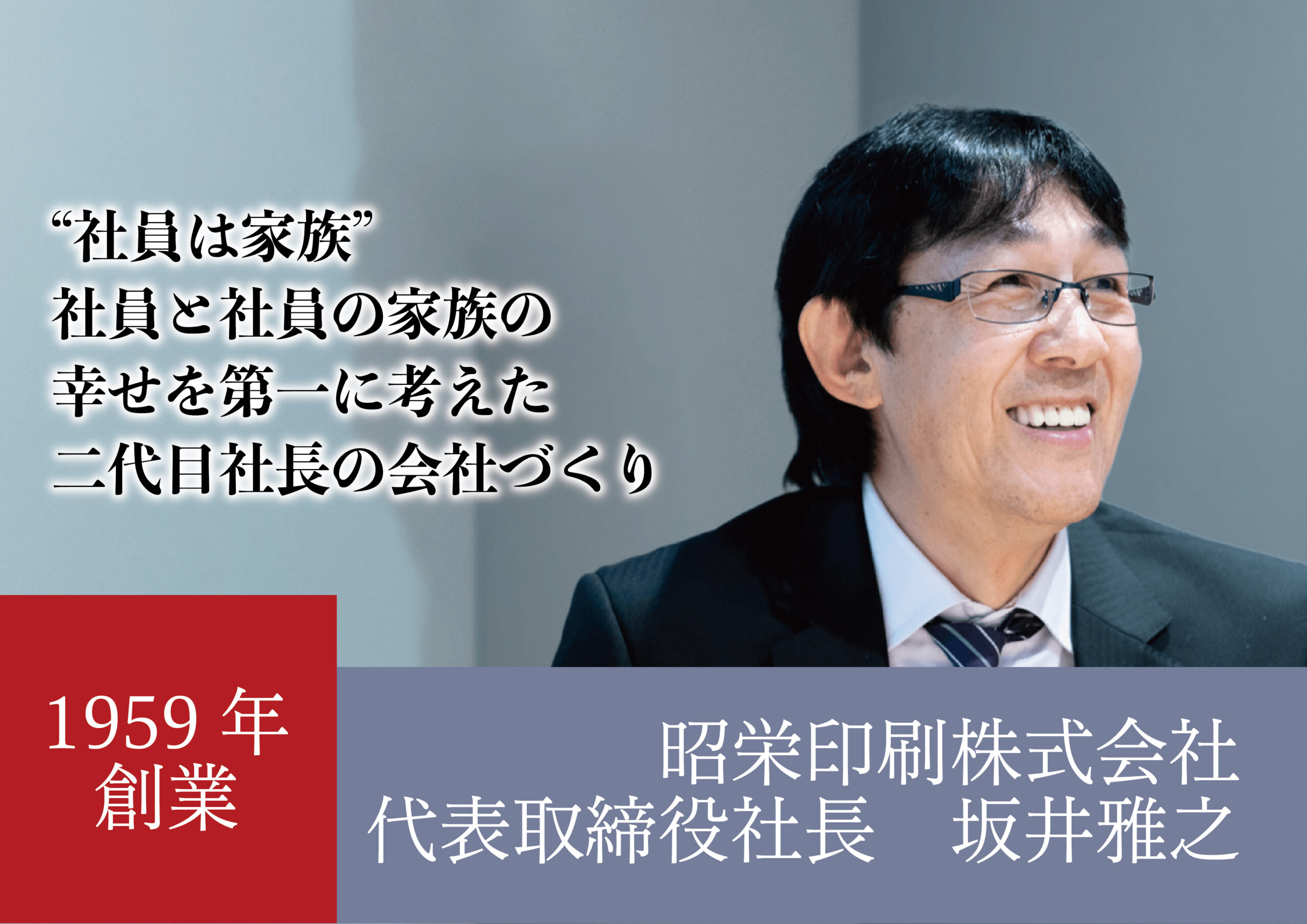
_トプ画.png)
_トプ画.png)
_トプ画.png)
監修企業からのコメント
この度は、取材のご協力をいただき誠にありがとうございます。
こめ油が他の油とどのように違うのかなど、こめ油についての知識や興味が高まり、こめ油の魅力に引き込まれる時間となりました。こめ油を活用した御社の今後の展望に目が離せません!
掲載企業からのコメント
今回の取材を通して、改めて弊社の事業優位性に気付けました。
今までこめ油に注げてきた愛情やこだわりはこれからも絶やすことなく紡いでいきたいです。また、今後も様々な事業に挑戦していきます。弊社の挑戦に興味を持っていただけましたら嬉しく思います。